循環器内科診療科・部門案内一覧へ戻る
.
当科は、急性心筋梗塞を含む冠動脈疾患や急性心不全などの循環器救急疾患を中心に加療を行っているが、その他、不整脈(脈の乱れ)・弁膜症・静脈血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)など、循環器全般の疾患を対象として診療しています。外来では、各種専門検査を行い、治療に難渋する症例についての紹介を積極的に受け、専門医療を行うと同時に、症状の安定した患者さまに関しては、地域のかかりつけ医の先生方と連携して慢性期の管理を行っています。
検査・治療法の特徴
カテーテル治療(手術)に関しては、狭心症などの冠動脈疾患に対する冠動脈インターベンション治療(ステント治療など)を中心に施行しています。
心臓の動脈硬化が進行し、非常に硬くなった石灰化病変には、ローターブレーターを用いて石灰化の切除も可能です。
また、当院では心筋梗塞やステント内再狭窄などの血栓の治療に、エキシマレーザーを採用しています。
心臓の動脈硬化が進行し、非常に硬くなった石灰化病変には、ローターブレーターを用いて石灰化の切除も可能です。
また、当院では心筋梗塞やステント内再狭窄などの血栓の治療に、エキシマレーザーを採用しています。
.
検査・手術実績
2024年度の手術及び検査実績
| 手術名・処置名 | 件 数 |
| 心臓カテーテル検査(検査のみ) | 126件 |
| 冠動脈インターベーション(PCI) | 84件 |
| ペースメーカー植込術(電池交換含む) | 42件 |
| カテーテルアブレーション | 42件 |
.
医師紹介
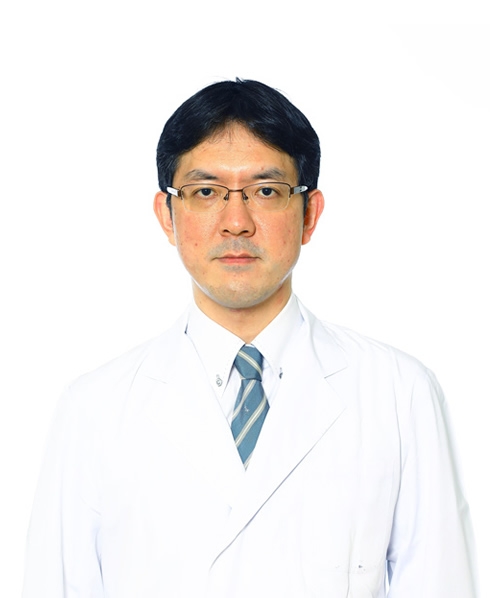
第六内科部長
川田 泰正かわだ やすまさ
高知医科大学 平成14年卒業
専門分野循環器一般、虚血性心疾患に対するカテーテル治療
指導医・専門医・認定医
日本内科学会認定総合内科専門医、日本循環器学会循環器専門医、心血管カテーテル治療専門医、日本不整脈心電学会植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療研修修了医、医学博士

医師
髙橋 誠たかはし まこと
高知大学 平成25年卒業
専門分野循環器内科
指導医・専門医・認定医
日本内科学会認定内科医、心臓リハビリテーション指導士認定医、日本心血管インターベンション治療学会認定医、日本循環器学会認定循環器専門医、指導医養成講習修了
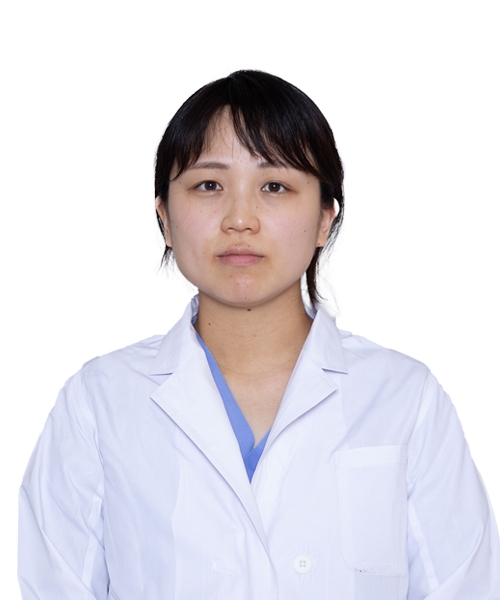
医師
森澤 公美もりさわ くみ
高知大学 令和3年卒業
専門分野
指導医・専門医・認定医


